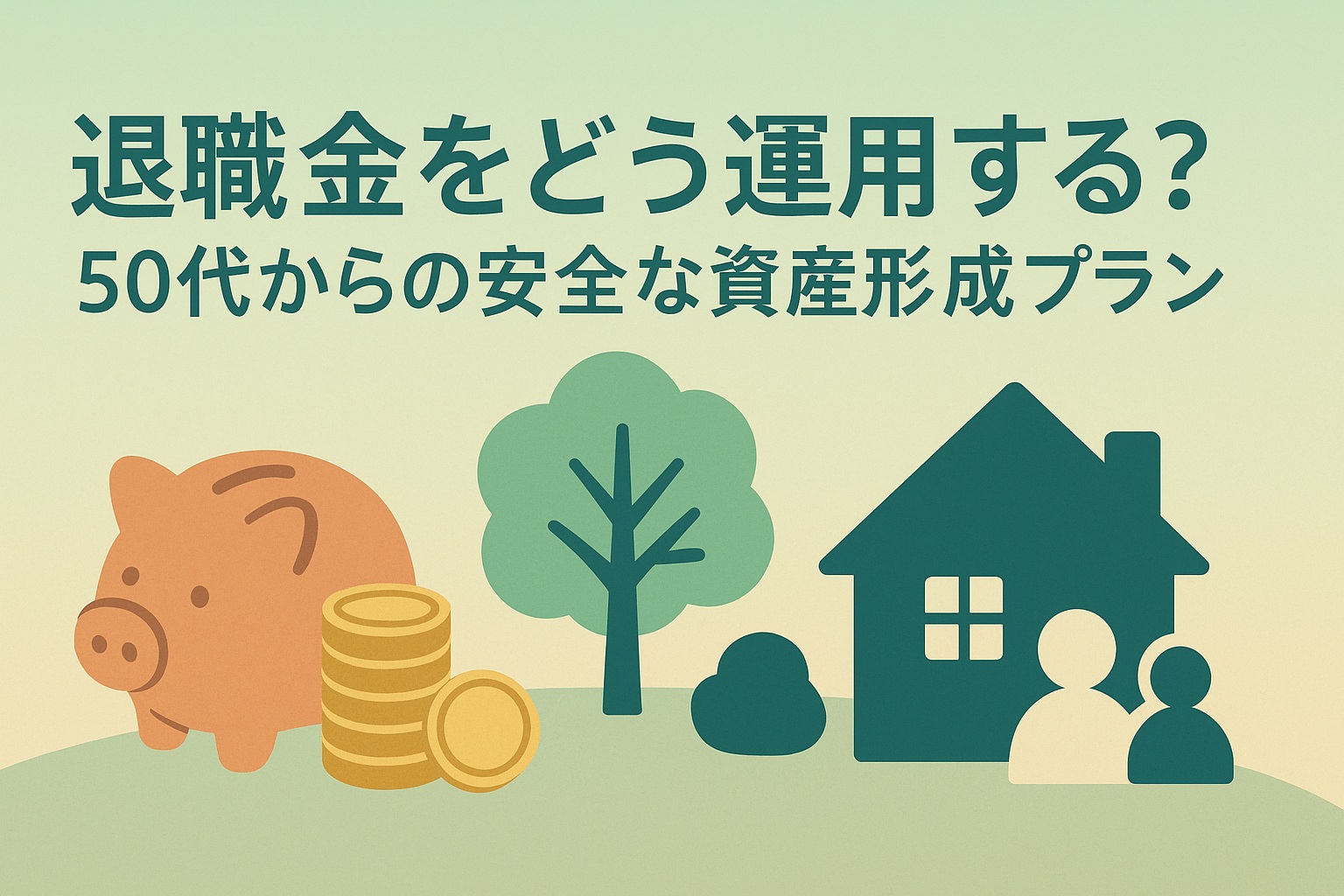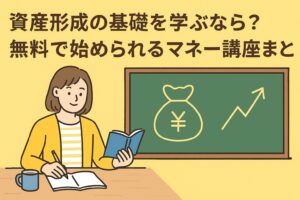はじめに
退職金は、多くの人にとって「人生で最も大きな一時金」です。
銀行に預けておくだけではインフレに弱いし、かといって株やFXなどの高リスク投資に全額を入れるのも不安…。
50代から大切なのは、「守りながら増やす」資産運用 です。
この記事では、退職金を安心して運用するための考え方と安全なプランを中心に紹介し、あわせて運用以外の選択肢についても触れていきます。
退職金を運用する前に考えるべきこと
退職金の運用を始める前に、まずは次の点を確認しておきましょう。
- 老後の生活費をどれだけ現金で確保しておくか
- 公的年金やその他収入の把握(夫婦で受け取れる年金額など)
- 一括投資ではなく、段階的に資産を分ける意識
👉 生活費や緊急時の備えは必ず現金で残し、余剰分を運用に回すのが基本です。
50代が退職金運用でやってはいけないNG例
「退職金を増やそう」と考えるあまり、次のような行動はリスク大です。
- 退職金全額を株や投資信託に一括投資する
- 短期間で大きな利益を狙う
- 知識がないまま仕組み商品や高リスク投資に手を出す
👉 特に退職金は「生活の土台」。失敗するとリカバリーが難しいため、堅実さを優先しましょう。

50代からの安全な資産形成プラン3選
① 投資信託・インデックス運用
- 全世界株式やバランスファンドで広く分散
- 積立NISAやiDeCoと組み合わせると税制メリットも
- 少額からコツコツ始められる
👉 初心者でも使いやすい証券口座は 楽天証券 や SBI証券 がおすすめです。
② ロボアドバイザーで自動運用
- WealthNaviや投信工房など、おまかせ型のサービス
- 自分のリスク許容度を選ぶだけで自動分散してくれる
- 忙しい50代・投資初心者に向いている
👉 手軽に始めたい方は WealthNavi をチェックしてみてください。

③ 預金や債券との組み合わせ
- 退職金の一部は定期預金や個人向け国債に
- 「生活費用」と「運用資金」を分けると安心
- 運用資金は少しずつ増やし、無理をしないことが基本
退職金の「運用以外」の選択肢もある
運用だけが退職金の使い道ではありません。
- 生活防衛資金として確保する
- 住宅ローンの繰上げ返済
- 保険や相続の見直し
👉 詳しくは関連記事「退職金の使い道一覧|運用以外の選択肢も解説」で解説しています。
私の体験談から感じたこと
私は積立NISAを15年以上続けており、現在は プラスで推移しています。
リーマンショックやコロナショックで評価額が下がった時期もありましたが、やめずに続けてきたことが結果につながりました。
退職金も同じで、一括ではなく“守りながら投資する姿勢” が大切です。
退職金運用を始めるステップ
- 証券口座を開設する(楽天証券・SBI証券など)
- 少額で分散投資をスタート
- 定期的に配分を見直す
👉 SBI証券の詳細はこちら
👉 楽天証券でNISAを始める
まとめ|退職金は「守りながら増やす」が基本
- 退職金は生活の基盤。全額投資はリスクが高い
- 「現金+運用」のバランスが安心感を生む
- 安全に運用するなら投資信託・ロボアド・債券の組み合わせが有効
- 運用以外の使い方もあるが、まずは「資産形成の仕組み」を持つことが重要
👉 まずは証券口座を開設し、自分に合った運用スタイルを少額から試してみましょう。
👉[楽天証券の詳細はこちら] |👉[SBI証券の詳細はこちら]|👉[マネックス証券の詳細はこちら]
⚠ 免責事項(ご確認ください)
本記事は筆者が調べた情報や一般的な考え方に基づいており、特定の商品や投資を推奨するものではありません。また、NISAや税制・社会保障制度は今後変更される可能性があります。最新情報は必ず金融庁や証券会社などの公的機関でご確認ください。投資判断は必ずご自身の責任で行っていただき、本記事の内容に基づく損失について、筆者および当ブログは一切の責任を負いかねます。