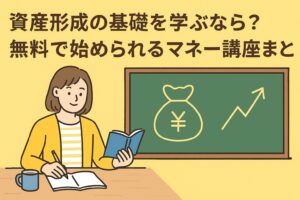目次
はじめに
「投資に興味はあるけれど、なんだか怖い」「失敗したらどうしよう…」
そんな気持ちを抱える方は少なくありません。特に50代になると、「今から始めても間に合うのかな?」という不安が強くなるものです。
でも実は、その不安の多くは 「知らないこと」から生まれているのです。基本的な仕組みや考え方を学ぶだけで、不安はグッと小さくなり、安心して一歩を踏み出せます。
この記事では、初心者でもやさしく学べるオンライン講座を3つ紹介します。私自身の体験も交えながら、学ぶことで「不安→安心」に変わる流れをお伝えします。
なぜ「学ぶこと」でお金の不安が減るのか
- 投資や資産運用は「分からないこと」が多いと、必要以上に怖く感じます。
- 書籍やネット記事は断片的な情報になりやすいですが、講座なら体系的に学べるので理解がスムーズ。
- 「リスクを避ける方法」「少額から始められる制度」など、知識を得るだけで選択肢がクリアになります。
- 50代からでも、基礎を学んで“少しずつ実践”すれば十分に間に合うのです。
お金の不安を解消できるオンライン講座3選
Udemy:自分のペースで学べる動画講座
こんな人におすすめ
- 忙しくてまとまった時間が取りにくい
- 何度も繰り返し復習したい
特徴
- 一度購入すればずっと見られる「買い切り型」。
- スマホでも視聴でき、スキマ時間を有効活用できます。
- 「投資信託の基礎」「NISA入門」など、初心者向けの人気講座が揃っています。
選び方のコツ
- まずは受講者数や評価が高い「初心者向け」を1本選ぶのがおすすめ。
- 受講後に必要なら、NISAや資産配分などもう一歩進んだ講座にチャレンジしてみましょう。
ストアカ:質問できる安心感が魅力
こんな人におすすめ
- 分からないことをその場で質問したい
- 人とのやり取りを通して理解を深めたい
特徴
- 講師と直接つながれる少人数制のオンライン講座が豊富。
- 「NISAの始め方」「老後資金の準備」など、実生活に役立つテーマが多いです。
- 初心者でも置いていかれにくく、安心して参加できます。
受講のコツ
- 事前に「疑問に思っていること」をメモしておき、講座中に質問して解消しましょう。
- 資料の有無も確認すると、復習しやすくなります。
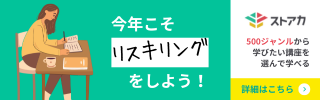
証券会社・金融機関の無料セミナー:信頼性で選ぶならここ
こんな人におすすめ
- 最新の制度改正や正確な情報を知りたい
- まずは無料で基礎を学んでみたい
特徴
- 大手証券会社や銀行が主催する無料セミナーは、制度の最新情報に強いのが魅力。
- 中立的に全体像を学べるので「誤解」や「思い込み」を減らせます。
- そのまま口座開設につながる流れも理解でき、実践に移しやすいです。
👉 [投資初心者におすすめの証券口座4選|50代目線で徹底比較]
👉[楽天証券の詳細はこちら] |👉[SBI証券の詳細はこちら]|👉[マネックス証券の詳細はこちら]
私の体験談|学んで「不安→安心」に変わったこと
私自身も最初は「投資って怖いもの」というイメージを持っていました。
ですが、講座で「リスク分散」「長期投資」「少額から始める方法」を学んだことで考え方が変わりました。
- 「株は大きく下がることもあるけど、少額で分散すれば怖くない」
- 「値動きは想定内、だから長く続けられる」
こうした理解ができると、不安は減り、月1万円からでも安心して積立を始められるようになりました。
今日からできるステップ
- 入門講座を1つ選んで受講
- 学んだことを踏まえて、少額で1つだけ実践(例:つみたてNISAで毎月1万円)
- 月1回だけ振り返り(講座の資料を見直す/投資額の調整を検討)
👉 さらに一歩進みたい方はこちらもどうぞ
まとめ|学びは安心への第一歩
- お金の不安は「知らない」から生まれます。
- まずは講座で基本を知り、少しずつ実践してみること。
- 小さな一歩が、不安を「安心」へ変えてくれます。
⚠ 免責事項(ご確認ください)
本記事は筆者が調べた情報や一般的な考え方に基づいており、特定の商品や投資を推奨するものではありません。また、NISAや税制・社会保障制度は今後変更される可能性があります。最新情報は必ず金融庁や証券会社などの公的機関でご確認ください。投資判断は必ずご自身の責任で行っていただき、本記事の内容に基づく損失について、筆者および当ブログは一切の責任を負いかねます。