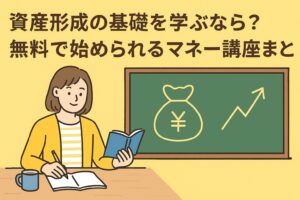目次
はじめに
「60代からNISAを始めても遅いのでは?」と思う方は少なくありません。
確かに投資を始める年齢が遅いと、時間を味方につける効果は小さくなります。
しかし実際には、60代からでもNISAを活用するメリットは十分にあります。
私自身も積み立てNISAを15年継続してきました。投資を続けているからこそ感じる「続ける意味」や「リスクへの向き合い方」を踏まえて、60代からのNISA活用ポイントを整理します。
60代からNISAを始めるメリット
- 年齢制限がない
NISAは年齢で制限される制度ではありません。60代からでも非課税枠を活用できます。 - 銀行預金よりインフレに強い
預金では資産がほとんど増えません。投資信託を通じて世界の株式や債券に分散することで、インフレリスクに備えられます。 - 配当や分配金が非課税
通常は課税される配当も、NISA口座なら非課税で受け取れるのは大きな利点です。
預金とNISAの違いを理解しておこう
NISAは「預金の代わりに安全に置いておける制度」ではありません。
預金と投資は仕組みがまったく異なります。
- 預金
- 元本保証がある(減らない)
- 金利はごくわずか(インフレに弱い)
- 銀行に預けておけば安心
- NISA(投資信託など)
- 元本保証はない(価格変動で増減する)
- インフレに対応できる成長の可能性がある
- 長期で積み立てるほどリスクが平準化されやすい
👉 「安心して減らない」=預金、「増える可能性があるが変動する」=NISA という違いを理解しておくことが大切です。
あわせて読みたい


投資初心者におすすめの証券口座4選|50代目線で徹底比較【NISA・使いやすさ・手数料】
はじめに 「50代になってから『証券口座を開くのはもう遅いのでは?』『手続きが面倒そう』と感じている方は少なくありません。実際、私の周りでも“銀行預金だけで十分”...
60代が意識すべきリスク管理
- 「増やす」より「守る」「使う」を重視
老後資金は生活費に直結します。大きく増やすより、安定して取り崩せる設計を意識しましょう。 - 投資期間が短いことを前提にする
30年の長期運用は難しくても、10年程度の運用なら現実的。短期間でも分散投資でリスクを下げられます。 - 一括投資より積み立てを優先
少額で分けて投資すれば「買った直後の下落リスク」を軽減できます。
60代に向いている投資スタイル
- バランス型投資信託
株式と債券が自動で組み合わされたファンドは、値動きが比較的安定しています。 - インデックスファンドの積立
世界全体や先進国に広く分散されたインデックスファンドは低コストで続けやすいのが特徴です。 - ロボアドバイザーを活用
WealthNaviやTHEOなどは自動でリスク調整してくれるため、「難しいことは任せたい」という方に向いています。
あわせて読みたい


50代から始めるロボアドバイザー入門|WealthNavi・投信工房の特徴とメリット
はじめに 「投資に興味はあるけれど、難しいことはよくわからない」「50代から始めても遅いのでは?」 そんな不安を持つ方に人気が広がっているのが ロボアドバイザー(...
私の体験談
私は積み立てNISAを15年継続しています。相場が下がる時期もありましたが、やめずに続けることで「長く続けるほど安心できる」という実感を得ました。
もちろんこれは私個人の体験であり、将来を保証するものではありません。
ただ、「続ける習慣そのものに意味がある」という点は、60代から始める方にも参考になるはずです。
60代からNISAを始めるステップ
- 証券口座を開設
→ 初心者でも使いやすいのは「SBI証券」や「楽天証券」です。
👉 [SBI証券の詳細はこちら]
👉 [楽天証券の公式ページはこちら] - 投資商品を選ぶ
→ バランス型インデックスファンドや、ロボアドバイザーの利用も選択肢。 - 少額から積み立てを開始
→ 月1万円など、生活に負担のない範囲で設定。 - 定期的に確認する
→ 年1回程度の見直しで十分。大きなリスクを取らないことが大切です。
まとめ
- NISAは60代からでも十分に活用できる制度
- ただし「預金」とは異なり、元本保証はない
- 重要なのは「増やす」より「守る」「安心して使える」視点
- 少額でも積み立てを始めることで、将来の選択肢が広がる
趣味や日常を楽しみながら安心した生活を送るために、まずは証券口座開設から一歩踏み出してみましょう。
👉[楽天証券の詳細はこちら] |👉[SBI証券の詳細はこちら]|👉[マネックス証券の詳細はこちら]
⚠ 免責事項(ご確認ください)
本記事は筆者が調べた情報や一般的な考え方に基づいており、特定の商品や投資を推奨するものではありません。また、NISAや税制・社会保障制度は今後変更される可能性があります。最新情報は必ず金融庁や証券会社などの公的機関でご確認ください。投資判断は必ずご自身の責任で行っていただき、本記事の内容に基づく損失について、筆者および当ブログは一切の責任を負いかねます。