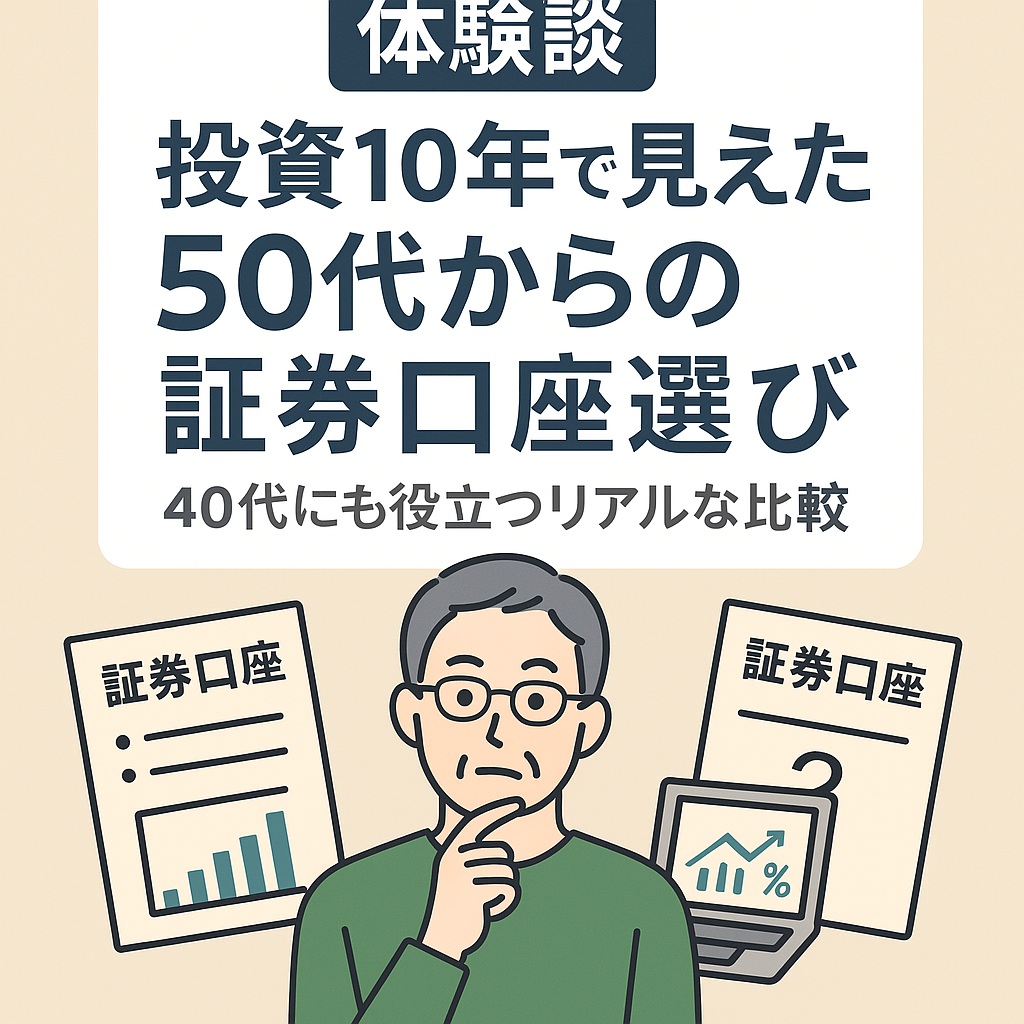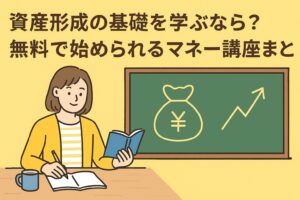はじめに
「50代から投資を始めても遅いのでは?」
「証券口座ってたくさんあって選び方が分からない…」
そんな声をよく耳にします。実は私自身も投資を始めたのは10年以上前、50代に入ってから本格的に積立NISAを続けています。さらに妻もSBI証券で同じように積立をしており、夫婦でコツコツと資産形成を進めてきました。
この記事では50代をメインターゲットに書いていますが、40代の方にとっても役立つ内容です。もし40代から準備を始めれば、老後までの時間をより長く活用でき、さらに余裕を持った資産形成が可能になります。
本記事では、楽天証券とSBI証券を実際に使ってきた体験談をもとに、年代別の視点も交えながら証券口座選びのポイントをお伝えします。
なぜ50代でも証券口座選びが大切なのか
投資を始めるためには、まず証券口座を開設する必要があります。銀行に預けているだけではNISAや投資信託は利用できません。
特に50代は「老後までの時間が限られている」という特徴があります。だからこそ、安心して長く使える口座を選ぶことが重要です。
👉 40代の場合は「教育費や住宅ローンと並行しながら投資を始めたい時期」。早く始めるほど積立効果を大きく得られます。
私の投資10年体験談
楽天証券を利用してきた私の場合
私は長く楽天証券を利用してきました。主に積立NISAを活用し、投資信託を毎月コツコツと購入しています。
選んだのは「全世界株式」「全米株式」「日経平均」「新興国株式」などのインデックスファンド。現時点ではプラスで推移しています。(※個人の体験談です)。
楽天証券の良かった点
- 積立設定がシンプルで分かりやすい
- 楽天ポイントを投資に使える
- サイトやアプリの画面が直感的
注意点としては、投資信託の商品数が多いので「最初はどれを選べばいいか迷った」こと、またリーマンショックやコロナショック時には大きく下落して気持ちが揺れたことです。
SBI証券を利用する妻の場合
一方、妻はSBI証券を利用しています。投資商品は私と同じくインデックスファンドを中心に積立。結果として成績もほぼ同じ運用成績になっています。
SBI証券の良かった点
- 投資信託のラインナップが圧倒的に豊富
- 手数料が低く、長期投資に有利
- ネット証券としての実績が長く安心感がある
デメリットを挙げるなら、楽天に比べると画面操作がやや複雑で、最初は慣れるまで時間がかかったことです。
👉 [SBI証券の詳細はこちら]
体験からわかった証券口座選びのポイント(年代別視点)
なんとなくリスク分散の意味合いを兼ねて夫婦で異なる証券口座を使っています。運用成績は、同じインデックスファンドを買えば成績はほとんど変わらないようです。
つまり大切なのは、
- 使いやすさ(アプリやサイトが直感的か)
- 低コスト(手数料や信託報酬が安いか)
- 安心感(運営実績やサポート体制)
さらに、年代別で意識するポイントは少し変わります。
- 40代:教育費や住宅ローンと両立させながら、余裕資金で積立を始める
- 50代:老後までの残り時間を意識して、堅実な資産形成を優先する
50代におすすめしたい証券口座(40代にも有効)
私と妻の体験から、特におすすめしたいのはこの2つです。
- 楽天証券
初心者にやさしい操作性、ポイント投資の使いやすさが魅力
👉 [楽天証券で始める] - SBI証券
投資信託の本数が圧倒的で、長期的に運用したい人に安心
👉 [SBI証券の詳細を見る]
まとめ|まずは一歩、証券口座を開設してみよう
「投資を始めるのは若い人だけ」と思われがちですが、40代・50代からでも遅くはありません。
実際に私も妻も、それぞれ楽天証券・SBI証券を使ってコツコツ投資を続け、成果を実感できています。
証券口座は複数開設しても問題ありません。40代ならより長い時間を、50代なら安心を重視した設計を──いまの年代から一歩踏み出すことが将来の安心につながります。
👉[楽天証券の詳細はこちら] |👉[SBI証券の詳細はこちら]|👉[マネックス証券の詳細はこちら]
⚠ 免責事項(ご確認ください)
本記事は筆者が調べた情報や一般的な考え方に基づいており、特定の商品や投資を推奨するものではありません。また、NISAや税制・社会保障制度は今後変更される可能性があります。最新情報は必ず金融庁や証券会社などの公的機関でご確認ください。投資判断は必ずご自身の責任で行っていただき、本記事の内容に基づく損失について、筆者および当ブログは一切の責任を負いかねます。